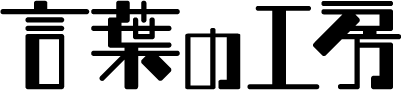外だけがやたら明るくて、校舎の玄関は真っ暗に見える。それは決して気持ちだけの問題ではないと思った。
「キモ」
ひとことだった。本当にこれだけ。ずっと悩んで、ようやく決心がついて。最初で最後のチャンスだと思って言った「好き」という告白の返事が「キモ」。
聞こえた瞬間終わった、と思った。明日になれば学校中に広まるだろう。罵られるのは慣れてる。嫌われるのも。だけど、彼と話もできなくなるのだけは嫌だった。やっと普通に話ができるところまで来たのに。なんでこんなこと言おうと思ったんだろうか。してもしきれない後悔。
「帰るわ、じゃな」
彼は面倒くさそうな顔のままローファーに履き替え、玄関を出ていった。安っぽいドラマのようだと思った。持っていたかばんがやけに重い。
あれ以来、ただの一言も話すことなく別の道を進んだ。卒業式だって目も合わせなかったはずだ。
大学時代は馬鹿みたいに遊んで、人に言えないこともして、彼のことは忘れたつもりでいた。忘れたはずだった。
就職だって地元ではしなかった。帰ってくるたびに刺さる視線に耐えられなかった。きっとそう思っているのは自分だけで、誰もなにも思ってないのかもしれない。だけどあの時の失敗はどうしてもぬぐい去ることはできなかった。
「ちょうどいいからお前も来いよ。みんな来てんだし、せっかく同窓会やるっつってんだからさ」
申し込みもしてないのにたまたま帰省してたところをつかまえられて、引きずられるように飲み屋に来た。同窓会とは名ばかりで、単に暇人が飲みたいだけだったようだ。髪もぼさぼさだし、カッコだって適当だし、なによりその場にいたくなくて早く帰るつもりでいたら、そこに彼がいた。
「よう」
何もなかったみたいに手をふってくる。あの頃よりもあかぬけた格好になってる。たしか都会の学校に行ってそのまま就職したんだっけか。
「ども」
自分でもびっくりするくらいにぶっきらぼうな返事になった。全然気にしてない様子に、ああ、忘れたんだ。よかった。そう思った。
同窓会は進み、結局手持ちぶさたになった自分の隣に彼がくる。注がれるビール。とてもじゃないけど飲む気にはなれなかった。
「俺のことまだ好きか?」
突然の言葉にこぼしそうになる。
ば、馬鹿か!
「ずっと気にしててさ」
思わず彼をにらみつけた。なんだそれ。自分が悪いみたいな顔するんだ。
「好きですよ、好きだよ? 当たり前じゃん。そうやって蒸し返してまたキモいとか言うんだろ」
精一杯鋭いトゲをつけた言葉のつもりだった。彼は全く気にしていないみたいにビールを飲む。
手に持ったコップの縁にかろうじて残った泡と、小さく小さく上ってくる炭酸が見えた。もう冷たいとは言えない温度だ。
「俺のどこがいいのさ」
「全部」
「そっか」
なんで刺さらないかな。よっぽど嫌だったか、本気で忘れたかどっちなんだろう。
「一言も話さなくなったくせによく言うよ」
コップを煽る。食道から胃にかけて苦味が走るのがわかる。
彼はビール瓶を手元でもてあそびながら、たぶん誰にも聞こえなくくらいの大きさで「ごめん」と言った。
二人して黙る。どっと盛り上がる声が部屋の反対側から聞こえて、一瞬こっちを見たような気がする。そしてまたすぐに笑う声がした。んだよ。こっちのこと馬鹿にしてんのか。
「よくわからないんだ。経験ないし」
どうしたらこの状況でそんなありきたりな返事が出来るんだろう。こっちの気なんか知ろうともしないで。
彼の持っていた瓶が汗をかいていて、服が濡れているのがわかる。なんとなくそのへんに置いてあった台ふきを彼に渡した。
「もういいよ。なかったことにして」
「でもまだ」
俺のこと好きなんだろ、とでも言いたげな顔をしてこっちを見ていた。やめろ恥ずかしい。
「もう顔を見せたりしないから、いいかげん忘れてくれないかな」
それだけ言うのが精一杯だった。
あの時だって彼を困らせるつもりなんかなかった。どうしてもどうしても好きだと伝えないと、自分がつぶれてしまいそうなくらいに苦しかっただけなんだ。それをいまここで言ったところで、彼はわかることはないだろうけれど。
同窓会(という名の飲み会)はまだまだという雰囲気を持ったまま一次会を終える。誰よりも先に帰ろうと支度をしていたら、彼から名刺を渡された。
「裏にケータイとメールとLINE書いてあるから」
とくに興味はなかったけれど、いいとこで仕事してるんだな、とだけ思った。初めて名刺を見た未開の地に住む人のように表裏を何度も見る。
「いつでも連絡してよ。仕事中でもわりと反応できると思うし。外回り多いから」
「そのうちするよ」
冷めるというのとはまた違う感情だな、と思った。やっぱ来るんじゃなかったな。二次会の話を後ろのほうで聞き流す。たまたま連れて来られただけだから、その後に誘われるようなことはなかった。そりゃそうだろうとは思う。
なにも知らないふりをして、じゃあ、とみんなと別れた。おつかれーす。またな。たまには帰ってこいよ、いろんな声が飛び交う。一つ一つ返事をするのは嫌だったので、彼からもらった名刺をひらひらと頭上で振って挨拶代わりにした。それを気にいられたと受け取ったのか、彼は大きく手を振りまわして、見送ってくれた。ようだった。
彼らがその後どうしたかは知らない。
もう会うことなんかないしな。酔いざましの水を買うために入ったコンビニで、もらった名刺をゴミ箱に捨てた。