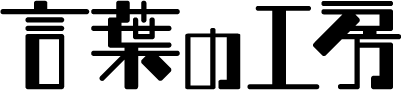さっきからずっとゲームをしてる。ユーレイは僕の友だちで、同じクラス。
ユーレイはふだんからいるんだかいないんだかわからないくらいの存在感で、だからみんなからユーレイと呼ばれてる。幽霊。本人は別にどうでもいいみたいな顔をしているけれど、たぶんものすごく気にしてるんだと思う。僕がいちどユーレイと呼んだことがあった時に、ものすごい勢いで怒ったのだった。あとにも先にもユーレイが怒ったのを見たのはその時だけだ。
ユーレイはたまに僕の家に来て、特に話をするわけでもなくひたすらゲームをするか、本を読むか、そうでなかったらベッドで一眠りしてから帰る。好きなゲームは救ったり助けたりする系のゲームだ。僕と違って、やっつけたり倒したりするようなゲームはしない。そういうのは嫌いなのだという。この前も100人助けたらゴールのゲームで95人しか助けられなかったといって泣いた。 ユーレイは僕の前でだけ泣く。
「どうしても地下にいる5人を助けられないんだ」
「でもそれを助けたら他でもっとダメになるんでしょ?」
「全員助けないと意味がないんだ」
こうなったら、もう僕にはどうしようもない。僕はユーレイのそばに行って座る。膝を立てて、その上にあごをのせて座る。無言でコントローラーを渡される。持つ。スタートを押して途中参加する。52、53、54。
途中二手に分かれる。画面も分割されて、僕は僕の、ユーレイはユーレイのルートにいる誰かを助ける。78、79、80。81、82。
また合流する。99、100。二人そろってゴール。
コングラッチュレイションズ!
僕はユーレイを助ける。ユーレイはみんなを助ける。本当のゴールは100人じゃなくて101人なのかもしれない。満足したユーレイは僕に抱きついてそのまま床に倒れる。僕はいつもどうしていいかわからずにそのままの姿勢で固まる。
ハグとキスはいつもセットだ。そしてそれ以上のこともする。たまにだけど。
学校ではユーレイは自分の席で本を読む。僕の家から持ってきた本だったり、自分の本だったり、図書館のだったりする。僕はそんなユーレイの背中とか横顔とかを見る。目の動きやページをめくる指の動き、僕の視線に気付いてこっちを見るときの頭の動きはいつ見ても飽きない。
今、ほんの少しだけ笑った。
「なに笑ってんだよ」
クラスの誰かがユーレイに聞く。
「いやなにも」
ユーレイの答えはいつもそっけない。僕の存在はユーレイの幽霊以下で、誰も気づかないふりをする。ユーレイは僕のことにふれないようにしている。僕を守るためと、自分自身を守るためだ。いつだったか僕の机の上に花瓶が置いてあったことがある。ユーレイはそれを黒板が見づらいからといってどこかに持っていってしまった。おもしろくない冗談だ、とあとで教えてくれた。
ユーレイの書く字はきれいだ。習字をいっしょに習っていた。僕はちっとも上達しなくて、先生に呆れられたことがある。ユーレイのノートはだからいつもとてもきれいで、みんな見せてほしいと思っているらしかった。僕はユーレイがえんぴつを走らせているところをずっと見ている。
学校の帰りもいつもいっしょだ。ユーレイが僕の家の前まで来てくれて、それから自分の家に帰る。母さんはいつもユーレイが家に来ることを申し訳ないと思っていて、ときどきおやつを渡そうとするけれど、ユーレイはいらないという。僕は母さんがこうやっておやつを渡してくれるから、誰かが僕と仲良くしてくれるのだということを知っている。僕にはおやつ以上の価値はない。
ユーレイは僕の部屋に来ると、借りていった本を本棚に戻し、新しい本をとりだす。僕のほうを向いて、僕の手をにぎる。キスとハグはいつもセットだ。何回かに一回は好きだったよ、といってくれた。過去形なのがちょっと残念だと思う。
僕たちは二人ともクラスの中ではハブられてた。だからいつもいっしょにいた。
何日か前、乱暴なやつらが僕らを囲んで、殴ったり蹴ったりしてきた。僕はユーレイがケガをするのが嫌だったから、ユーレイに覆いかぶさって酷い目に遭わないようにした。だけどそれはあまり意味はなかったのかもしれない。彼らは僕を引きはがして僕を執拗に攻撃した。僕の顔に、身体に、前にできたアザが消えないうちにまたアザが増える。
見ているだけでむかつくらしかった。同じ空気を吸うのが嫌なのだといった。むちゃくちゃだと思ったけれど、教室はたいていそんなむちゃくちゃなことだけに覆われていた。その光景はあまりに酷いので、誰も近寄ろうとしない。
一瞬、記憶が途切れる。なにが起きたのかも覚えていない。
「これ片づけるね」
ゲームに飽きたらしいユーレイは自分が出したわけでもないのにゲームの機械を片づける。僕はなにもせずにベッドの上に横たわっていた。ユーレイはベッドのそばに座ると、僕の頭を優しくなでる。
「ね、」
僕は声を出す。たぶん聞こえない。
「僕のこと、嫌いになってもいいんだよ」
声を絞るように出しても、きっと聞こえてはいない。
あの時からぼくの身体は動かない。起きているのかいないのかさえもわからないことがある。ユーレイが本当にここにいる人なのかどうかもわからなくなることがあった。僕が勝手に作りだしたものだったら。体中アザだらけでベッドに横たわっているだけの、なんの役にも立たない自分が作りだした想像上の友だちだったらどうしようかと、そう思えてしかたなかった。
ユーレイの手が僕の頬を暖めるようにつつむ。
僕は本当はしんだほうが良かったのだと思う。
動かせない唇と、出せない声でそう言うと、赤ん坊のように泣き出した。僕は一体どうしてしまったのだろう。
ユウイチ。僕はユーレイの名前を呼ぶ。聞こえなくても、何度も呼ぶ。
ユウイチ。
僕のほうを向いてくれた。お願いがあるんだ。
聞こえているのだか、聞こえていないのだかわからない声で僕はユウイチにお願いをする。
ユウイチは僕の顔を見て、ちょっと泣きそうな顔をする。ハグをしてキスをして、じゃあ、といって目を閉じた。
僕の顔に枕を押しつける。息苦しくなる。力いっぱい押しつけてくる。力が緩まることはない。だんだん苦しさが増してきて、僕はわけがわからなくなる。
意識が遠くなる。ユウイチ。ありがとう。じゃあね。そう言いたかったけれど、それは無理だった。