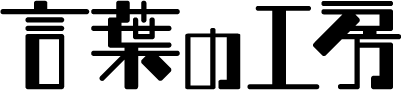もう夏というには涼しくなりすぎた頃のことだ。
日も暮れて、学校から帰ってきていた僕は宿題を早々に放り投げて興味もないテレビを見ていた。
開け放した窓から風がときどき入ってきて、カーテンが顔に当たるのがじゃまだった。
玄関で音がする。団地の金属製のドアを叩く音が廊下に響いて、風を通すために開けた隙間からすこし大きく聞こえた。
そのうち僕の名前を呼ぶ声が聞こえて、そこには見慣れた顔があった。彼女とは小学校の頃から仲が良く、中学では毎日のように遊んだ。高校は別になったからそれほど会うこともなくなったけれど、忘れたころに電話で近況を聞くくらいの関係はまだ保っていた。
「どしたの」
僕はまだ着替えていない、よれた制服を直しながら聞く。
「帰りのバスで変なおっさんに絡まれちゃって」
ずっと後ろからついてきて気持ちが悪いから友だちの家に寄るのだと、僕の家まで逃げてきたらしい。
「送ってってくれないかな」
「いいよ。ここのところ物騒だし」
入ってきたのとは別のところから建物を出る。人の多そうなところをわざと選んで歩く。普段なら僕たちが一緒にいるところを見られたくないから人通りの少ないところを選ぶのだけど、今日は特別だ。
なんか久しぶりだね。彼女は僕の顔を見もせずに言う。二人だけで歩くのって初めてじゃないっけか。僕はときどき周りを見て、変なおっさんがいないか確認をする。それはまるで見られてはいけない関係をどうにかして隠そうとしているみたいだった。
「彼氏か誰かいなかったっけか」
「今はいないよ。アタックしてる人はいるけど、他に誰かいるらしいし」
「前言ってた人?」
アルバイト先の、僕よりも背が高くてバンドをやっている、雑誌のモデルにいそうな顔立ちの人。
いつだったか電話で話したときに、かっこいいからつきあいたいと聞かされていた。間違いでなければ歌手のあれか、あれに似ているんだろう。
僕じゃだめなんだろうか。周りを警戒しながらそんなことを思った。すぐに頭から消した。
大通りの信号をひとつ分歩いたところで僕たちは無言になった。僕が聞きたいことがずっとあって、でも聞くわけにはいかなくて、なにを話したら雑談になるのかわからなくなっていた。
ときどき彼女のほうを見た。何回かに一回、気づいてこっちを見てくれた。
「あたしさ」
大通りに出てふたつ目の信号のあたりで声が聞こえた。僕は声がかすれてるなと思いながら返事をする。なに?
「ほんとはずっと好きだったんだよね。今は、」
言葉は続かなかった。そんなところで止めるのはずるい。だけど僕はその先を聞く気はなかった。僕よりも好きな人がいるのは知っている。
「俺はまだ好きよ」
「知ってる。ふたりして片思いだったんだよね」
僕たちはあの時はこうだったとか、その時にもう気づいてたとか、そんなことで盛り上がった。どんなことばを使って君の本心に近づこうとしても、うまくかわされてた。
「なんではっきりさせなかったのかな」
「すぐはぐらかすじゃん」
今みたいに。聞こえるか聞こえないか、それくらいの声は呪文のようだ。もう無理だよ。
信号を越えて、川沿いの道に入ったと同時に、彼女は僕の腕を取った。そういうところが良くないんだ。いつか悪いやつに騙されても知らないぞ。言葉は頭をぐるぐると回り、辛うじて出そうになった声は川の流れに消されてしまう。
「また遊ぼうよ」
僕は当たり障りのない言葉を、ようやく絞り出した。そんなこと叶うなんてこれっぽっちも思ってなかった。キスでもできたらよかったのかもしれない。そう思ってすぐに捨てた。サイテーな男と同じことしてどうする。
「ダメだったらね」
彼女はもしかしたら全部わかっていたのかもしれない。いつもなら冷たく聞こえる言葉に今は救われている気さえした。
「あんまりくっついてるとお父さんに叱られるだろ。とばっちり受けるの嫌だよ」
彼女の家が目の前まで迫る。僕はなかば無理矢理、彼女の腕を解いた。
「なんかあったら言ってよ。送るくらいしかできないけど」
すこしずつ、離れていく。彼女の顔を見た。さっぱりしたような、興味がないような、少なくとももう僕とは会うことはないような、そんな表情をしていた。
「ありがと。気をつけてね」
「おっさんは俺には用はないだろ」
「おっさん受けする顔してるじゃん」
ひっでえ。僕たちは最後の最後で笑った。どこかの家の犬が吠えて、近所迷惑になることに気がつき、深呼吸をして落ち着こうとした。
「またね」
僕たちは手を振って別れた。
それから連絡を取り合うことは二度となかった。