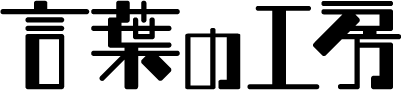ときどきうしろを振り返って君にレンズを向ける。なんだよう。少しだけしかめつらをした君を捉えてシャッターを切る。
「もうちょっとマシな顔を撮ってくんないかなあ。なんかだいなし」
ペットボトルのキャップを開ける。少しだけ口をつけて、顎をくっとあげて飲み物を流しこむ。いつ見てもCMみたいな飲みかたをするなあって思う。これもカメラに収める。
「なに、好きなの?」
「うん」
写真を撮るのがね。僕は曖昧に答えた。
ぽっかりと数日空いてしまったので、僕たちはなにも決めずに旅行に出た。ふたりとも学校帰りみたいな荷物しか持っていなかった。僕のほうはいつも持ち歩いているカメラも一緒だ。車窓から見えた景色が僕たちを呼んでいたら降りる、みたいなゆるいルールを決めて、なんとなくこの町で降りた。いつもは使わない路線に乗って、しばらくはそれぞれがそれぞれのことをして、会話もなく列車は進んだ。いくつかトンネルを抜け、海が見えたら急に降りてみたくなって僕は「ここで降りよう」と言った。
「思ったよりなんにもなかったな」
「まあでもいいんじゃない。泊まるところはありそうだし」
防波堤の上を手を広げて君が歩く姿を、僕はファインダー越しに追う。シャッターを切る音が海の音に消されるのがわかる。
「コンテストとか出すー?」
「なにを?」
「いま撮った写真」
なんだ気がついていたのか。僕は恥ずかしくなってカメラのディスプレイでなにが撮れたか確認するふりをする。
僕たちが所属している、大学の写真サークルは部員が少ない。僕たちのほかは上に三人、下は二人。全部で十人にも満たない。定期的にコンテストに応募しては誰かがいつも入賞している。
フードを持ってくればよかった。なんだか中途半端に光線がジャマして画面がうるさくなっているような気がした。
僕が撮る写真はいつも余計なものが多すぎると言われる。今日も堤防と空と君しかいないのになんとなくうるさい感じになっている気がする。
キラキラした写真なんかリア充が撮ればいいんだ。
先輩は事あるごとにそう言っていたし、実際、普段から僕の撮る写真への評価は渋く、硬派な写真を撮る人が多かった。だから部員が少ないんですよと僕は言うべきだったのかもしれないし、僕のように、ふわふわとした写真を撮るのなら、ここではなくて別のところに所属すべきだったのかもしれない。なんにせよ、サークル全体の作風からすれば、僕のような写真は浮いていることになる。
堤防から飛び降りた君が僕の手元をのぞく。
「見んなよ恥ずかしい」
「えー。これいいじゃん。いつもよりもいい感じ」
これが? 僕は納得いかない。ディスプレイには、手を広げて逆光で影になった君に、斜め上から降り注ぐ光の玉が見えた。こんな光の玉をゴーストという名前で呼ぶのはなんかきれいすぎると思う。
「フード持ってくればよかった」
「持ってないの?」
「めんどくさい」
そんなんだから上にボロクソに言われるんだよー。君はびっくりするくらいの大声を出した。そしてたぶんそれは正しい。
「でも、これはいいんじゃないかなー。うん。好きだよ」
小洒落たバンドのプロモーションビデオじゃないんだからさ。こんなにジャマしてたらだめでしょ。僕はそういう写真を撮るのは避けている。だからいつもゴーストが入らないように気をつけていたのだけれど。なにがよくなかったんだろう。たぶんフードつけたらそれですむ話なんだろうけど。
「この前、名前だけ載ってたの見たよ」
君はそういうことにはやたら目ざとくて、一次通過とか佳作とか名前しか載らないようなものでもすぐに見つけてきた。
「モデルやるからさ、もうちょっとでかいコンテストに出しなよ」
今日だってそのつもりだったのだろう。僕なんかよりずっとちゃんとした写真を撮るのに、一式を持ってこなかった。カメラはただの趣味だから、と笑っているけれど、本当はなにを考えているのかはわからなかった。
夕飯を済ませ、宿のテーブルで僕たちはパソコンを広げていた。画面にはさっき僕が撮った写真。RAWファイルというなにも加工していないデータから誰でも見られる写真データに「現像して」いた。ほら、やっぱいつもより全然いいよ。君は少し興奮気味に画面を指差す。そうかなあ。僕は今ひとつ納得できずにいた。人物にかかるように出たゴースト。空が白く飛んでいるのも好きじゃない。
「これ、失敗じゃない?」
「堅っ苦しく考えすぎなんだよ。いくら硬派な人が多くてもさ、無理に合わせて本当に得意な撮りかたとか、目線とか捨てちゃどうしようもないよ」
あの人たち、頭固いからさ。あんなガチガチじゃ部員も集まるわけないって。君はパソコンから離れると缶ビールを開け、将来の名カメラマンにかんぱーい、と何度目かの乾杯をした。飲みすぎだよ、それ。
「例えばだよ」
君は、そういえば見せようと思って持ってきたんだった、とばかりにカバンの中からファイルを取り出して広げた。
「これとか、いつも撮ってるのとぜんぜん違っていいと思うんだ」
ファイルに収められていたのは、いつだったかまぐれで入賞したコンテストの写真だった。大学に入る前に、カメラを手に入れたうれしさだけで撮って、その勢いで応募したやつだ。晴れた公園の丘と、そのとき一緒にいた友だちと、友だちがナンパした知らない人の犬。露出はめちゃくちゃだし、水平だってとれてないし、たぶんピントだってあやしい。なんでこんなの応募したのかわからない。そしてこれが入賞したのだってきっとなにかにだまされてるんだと思った。
たとえばキラキラした笑顔とか。
「偶然にしちゃ狙いすぎだよ。選評だってちっともほめてるように見えないし」
「でもこの人のこと好きだったんでしょ。たぶんこの人もそっちことが好きだね。それが伝わってくるんだから、これはいい写真」
図星を突かれていた。写真に撮った相手には最後まで本当のことは言わなかったけれど、僕はその人のことを好きだった。相手はどうだったのかわからない。僕にはなにも言ってくれなかったし、僕がなんとなく聞いたときも「さあね」といってはぐらかすだけだった。今はどこに住んでいるか知らないし、たぶんもう会うこともない。ポストに「元気でね」とだけ書かれたハガキが入っていて、僕の隠しておいた気持ちは最後まで外に出ることはなかった。
「ていうかなんでこんなもん持ってるんですか」
僕は変なことを思い出して動揺しているのを隠そうとして失敗していた。あわててるねえ。君は僕の視線が部屋中を移動しているのを見て笑った。
君は僕の入賞作が載っているページの上のほうを指さした。僕のよりも何倍も大きく掲載された写真と、コメント、今じゃ考えられないくらい仏頂面した君の顔写真があった。僕は何度もファイルと君の顔を見比べる。
「なんか偉そうなこと言ってるけど、これ見たときに負けたなあって思ったんだよね」
編集部の人にこの写真取った人紹介して、って言ったんだけど教えてくれなくて、ケチだなあって思ってたら同じサークルになると思わなかった。君と君の言葉が距離を詰めてくる。顔の位置がやたら近い。ふだん飲まない酒のせいかなんなのか、心臓の音が爆音で頭と胸に響いてくる。
「勢いだけじゃダメなのはもちろんそうなんだけど、もっと思い切らなきゃダメなこともあるんだと思うよ」
というわけで勢いで抱きつきまーす。宣言した君が勢いをつけて僕に抱きついてきた。酔っ払った息が酒臭かったけれど、それはきっと自分も同じだと思うと、僕はもう身をまかせるしかなかった。
「二日酔いしてない? 大丈夫?」
心配する僕なんか構わずに、君は波打ち際で一人、びっくりするくらいの大声を出して遊んでいた。まだ朝早いんだからさ、近所迷惑とか考えようよ。
「大丈夫だよー。早朝っていい写真撮れるからさー。たくさん撮ってよ。そんでコンテスト出そう」
まだ言ってる。僕は、はいはい、撮りますよ、とか、こっち向かなくていいよ恥ずかしいから、とか言いながらシャッターを切った。
撮影場所を移動しながら、撮れた写真を確認する。あちこちから反射してきた光が浮かびが上がらせたい被写体を邪魔をしてしかたない。
「これいいよ。これ候補ね」
「勝手に決めんなよ。こんなキラキラした写真なんかやだよ。リア充じゃあるまいし」
「なに言ってんだよ。また逃げられるぞ」
それを言いたいのはこっちのほうだ。なに言ってんだよ。
僕のカメラを横取りしてディスプレイを見ていた君が、乱暴に返してきたかと思うと、そのまま波打ち際に向かって突進していった。
たのしいいいいいいいいい!
馬鹿だコイツ。濡れたらどうすんだよ、着替え持ってないじゃん。僕は呆れていた。だけどシャッターを切る事は忘れなかった。
海に反射した光と、太陽から降ってくる光が君をシルエットに変えるように照らしている。まぶしくて目を細めると、まつげの先が光を反射してたくさんのゴーストを作り出していた。空だって白く飛んで、君がはしゃぐ影を浮かび上がらせている。
突然、なにかが降りてきた。
目の前の景色を全部そのまま写真に収めたい。
どうやったら見たままのこれを撮れるんだろう。撮って君に見せたい。
僕が見ている景色はこれだって。
グリップを握る手に力が入る。シャッターを切る指は震えていた。落ち着くんだ。見ているとおりの絵になるように調整すればいいんだから。
思いついてほんのすこし絞りを開けて構える。たぶん明るすぎてまともな写真にはならないだろう。ファインダー越しの君はどんな顔をしているかわからないけれど、僕がなにをしようとしているか気づいたらしく、こっちを向いて大きく手を振った。
もう二度と僕の前から誰もいなくならないでほしい。僕は言葉にする代わりに何度も何度もシャッターを切った。